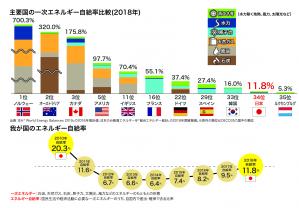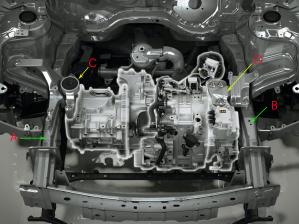「常識」は、つねに変わる。ものづくり大国ニッポンは本当なのか!? 日本人の勤勉さと「すり合わせ」の巧さを生かせる時代がまた到来した【牧野茂雄の自動車業界鳥瞰図】
- 2019/04/15
-
牧野 茂雄

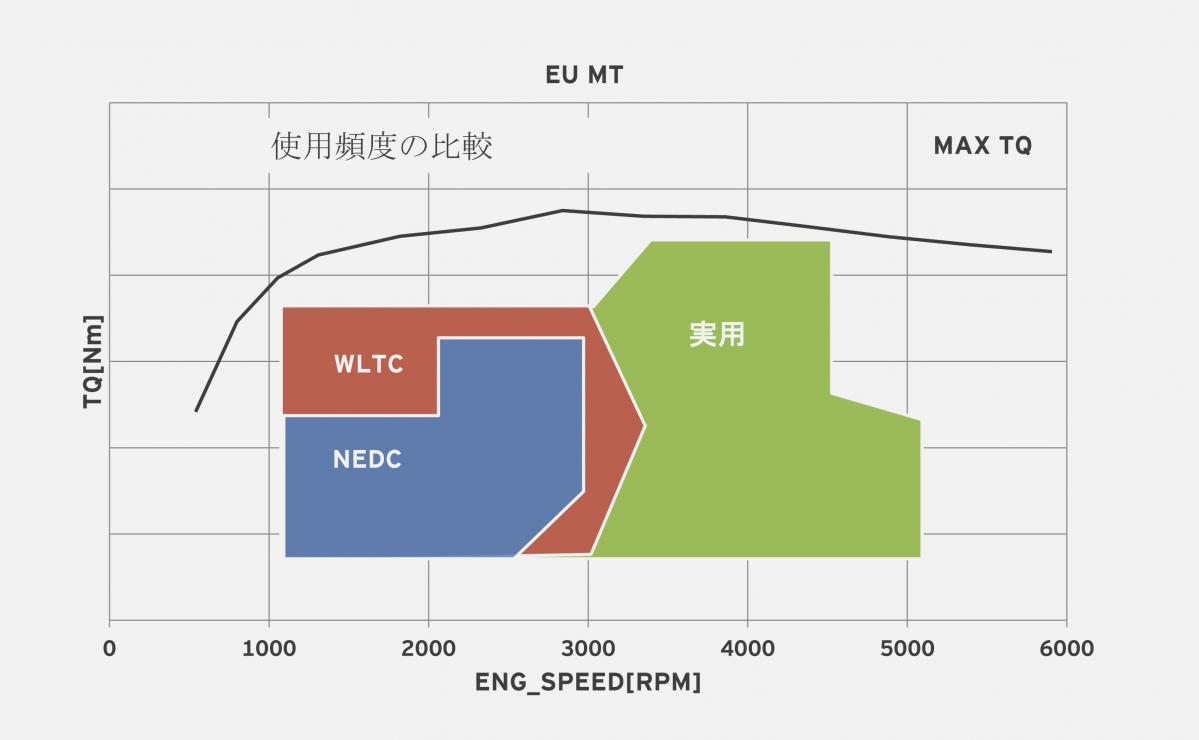
内閣府所管のSIP(戦略的イノベーション創造プログラム)に、自動車用内燃機関技術の底上げを目指した「革新的燃焼技術」というプロジェクトがある。日本の大学と自動車メーカー・部品メーカーが協力し、次世代エンジンのための基盤技術確立を狙った。そして大きな成果を残した。旧来の常識がいくつか破られ、新しい常識が生まれたのである。
TEXT◎牧野茂雄(MAKINO Shigeo)
日本のものづくりは優秀だ──そう思っている方がほとんどだろう。とくにものづくり企業のトップがこれを信じて疑わない。しかし、技術開発系や生産部門の責任者や役員のなかには懐疑的な見方の人が少なくない。ものづくり大国ニッポン。この標語は、多くの日本人にとっても常識化している。
日本の自動車は素晴らしい性能だ──多くのユーザーはこう思っているに違いない。燃費が良く、故障が少なく、見た目も手で触れる場所も品質が高い、と。しかし、開発の中枢や技術系役員の間では、世間一般とは少々見方が違うことも少なくない。当事者だけが感じる危機感というものがある。クルマづくりがなにか新しいステージに入りかけているという印象を抱いたとき、「いままでの常識はそろそろ捨てるべきなのか」という危機感だ。
では、自動車エンジンについてはどうか。日本のエンジンは世界に誇れるだろうか──私の答えは「Yes」だ。
日本のエンジンは、日本人が得意とする「すり合わせ技術」によって絶妙なバランスで設計され、どの部品も手抜かりなく、思い切った手法よりも確実性を重んじ、生産ラインでは入念に組み立てられる。同時に、そのエンジンが使われる仕向地ごとに、じつに細かな対策が施されている。そしてなにより、性能対価格比、コストパフォーマンスが抜群に高い。
そういうエンジンを産む研究開発の現場は、熱心な技術者諸氏で支えられている。私が過去に取材で話を伺ったエンジン技術者諸氏はたぶん2000人を超えるだろう。印象に残っている方々は多い。
しかし、私個人の印象でいえば、欧米の自動車メーカーやエンジニアリング会社に比べるとエンジン開発組織の運営が弱い。その背景は終身雇用にあると個人的には思う。欧米では人が入れ替わることを前提に知見の属人化を防ごうとする。なるべく情報共有し、外からの情報収集も怠らない。近年は最適解を外部に求める傾向が強いが、社内も参加したコンペの結果であると見れば、組織としての目標はじつに明快だと受け止めていいだろう。
もう一点、日本でのエンジン開発はユーザー目線で行なわれる場合が多い。「客さんに喜んでもらえるか」「これをやっても、違いはわかってもらえないだろう」「うれしさがなければお金は払ってくれない」と。一方、欧米は「これが正しい」「こうあるべきだ」がおもな動機だ。どちらも正しいし、日本のエンジンが技術的に劣っているわけではない。しかし、新しいものをとにかく使ってみるという姿勢は、日本ではごく稀である。
情報収集は日本が遅れだした。以前は、世界中のモーターショーや展示会、カンファレンス、シンポジウムをまわり、そこで見聞きしたことを本社に報告する専門要員を抱えている例が多かったが、2010年代に入り情報収集は外部頼みになった。そして開発現場は、目の前にある多くの課題をこなすことに追われ、個人の担当範囲は細分化され、全体を俯瞰する視線が足りなくなった。
5~6年ほど前に、ある自動車メーカーでディーゼルエンジンを取材したとき、若い技術者氏がこう言った。
「スワールを使おうなんて、もう古いです。多噴孔インジェクターから燃料が出た瞬間に着火するのですよ。せっかくの着火を横方向に回すなんてナンセンスです。これからは縦です」
スワールとは、吸気がシリンダーヘッド冠面とほぼ平行に、ピストン壁面を這うように旋回する横方向の渦である。これを聞いて上司がすかさずこう言った。
「こいつ、そういうことを言うんですよ。そんな証拠なんて見たことがない。タンブルなんてピストン上昇によってめちゃくちゃに壊されるはずです」
タンブルは縦方向の渦だ。当時の欧州ですでに発表されていた論文を読むと、たとえば燃料インジェクターの噴孔数が8の場合は隣の燃料噴流の拡散と干渉しないよう360÷8=45度の半分程度、22度あたりがスワールの最適値だという解析結果が書かれていた。筒内に燃料を直に噴射する直噴ディーゼルの場合、燃料が空気と混ざり合う時間が短いから、できるだけ吸気の流動を大きくするという燃焼室設計が主流だった時代に、スワール懐疑論が解析証拠付きで示されていたのだ。
その後、トヨタが新しいディーゼルエンジンであるGDシリーズを投入したときに設計チームから「燃料インジェクターの噴孔数から勘案し、スワールはほんの少しだけ」と聞き、あぁ、あの論文は本当だったのだなと納得した。トヨタの技術者諸氏はきちんと証拠を見せてくれた。シミュレーションと実機での解析はほぼ一致していた。スワールではなくタンブルを使うにはエンジンブロックの設計見直しが必要だったが、エンジン刷新のチャンスが約10年に一度である以上は「できるだけ多くの知見を織り込みたい」とのことだった。
- 1/2
- 次へ
|
|
|
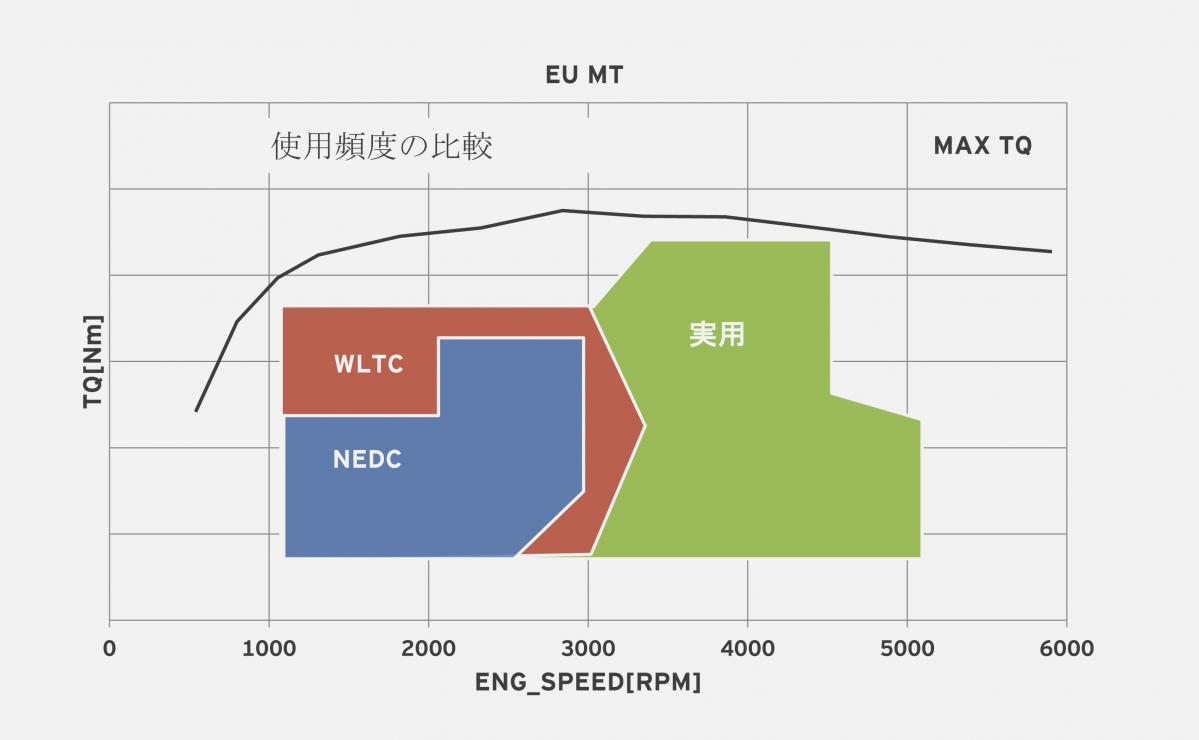
自動車業界の最新情報をお届けします!
Follow @MotorFanwebおすすめのバックナンバー
自動車業界 特選求人情報|Motor-FanTechキャリア
「自動車業界を支える”エンジニアリング“ 、”テクノロジー”情報をお届けするモーターファンテックの厳選転職情報特集ページ

東証プライム、ジェットエンジンが強みの重工メーカー
調達戦略立案・業務高度化の企画<航空・宇宙・防衛事業>
年収
640万円〜1050万円
勤務地 東京都昭島市
この求人を詳しく見る
AZAPAエンジニアリング株式会社
モデルベース開発エンジニア<農機用エンジンECU>
年収
400万円〜800万円
勤務地 大阪府堺市大阪府堺市の顧客先での就業...
この求人を詳しく見る
「自動車業界を支える”エンジニアリング“ 、”テクノロジー”情報をお届けするモーターファンテックの厳選転職情報特集ページ

東証プライム、ジェットエンジンが強みの重工メーカー 調達戦略立案・業務高度化の企画<航空・宇宙・防衛事業>
| 年収 | 640万円〜1050万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都昭島市 |
AZAPAエンジニアリング株式会社 モデルベース開発エンジニア<農機用エンジンECU>
| 年収 | 400万円〜800万円 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府堺市大阪府堺市の顧客先での就業... |
これが本当の実燃費だ!ステージごとにみっちり計測してみました。

日産キックス600km試乗インプレ:80km/h以上の速度域では燃費が劇...

BMW320d ディーゼルの真骨頂! 1000km一気に走破 東京〜山形往復...

日産ノート | カッコイイだけじゃない! 燃費も走りも格段に洗練...

渋滞もなんのその! スイスポの本気度はサンデードライブでこそ光...

PHEVとディーゼルで燃費はどう違う? プジョー3008HYBRID4とリフ...

スズキ・ジムニーとジムニーシエラでダート走行の燃費を計ってみた...
会員必読記事|MotorFan Tech 厳選コンテンツ

フェアレディZ432の真実 名車再考 日産フェアレディZ432 Chapter2...

マツダ ロータリーエンジン 13B-RENESISに至る技術課題と改善手法...

マツダSKYACTIV-X:常識破りのブレークスルー。ガソリンエンジン...

ターボエンジンに過給ラグが生じるわけ——普段は自然吸気状態

林義正先生、「トルクと馬力」って何が違うんですか、教えてくだ...

マツダ×トヨタのSKYACTIV-HYBRIDとはどのようなパワートレインだ...
3分でわかる! クルマとバイクのテクノロジー超簡単解説

3分でわかる! スーパーカブのエンジンが壊れない理由……のひとつ...

3分でわかる! マツダのSKYACTIV-X(スカイアクティブ-X)ってな...

スーパーカブとクロスカブの運転が楽しいのは自動遠心クラッチ付...

ホンダCB1100の並列4気筒にはなぜV8のようなドロドロ感があるのか...

ホンダ・シビック タイプRの謎、4気筒なのになぜマフラーが3本?